本日ご紹介するのは、地元「銚子市」の「偉人」「濱口吉兵衛」です。
「濱口吉兵衛」は、「ヒゲタ」を「ヤマサ印」、「亀甲萬印」と共に「醤油界」における「ブランド」としての地位を確立、明治後期「中央財界」で活躍し、「矢野恒太」とともに「第一生命」を興した「人物」として知られています。
「銚子醤油」(現「ヒゲタ醤油」)・「千葉県水産社長」、「濱口理事」、「武総銀行取締役」、「第一相互貯蓄銀行」・「東京護謨工業」・「第一生命」・「豊国銀行」・「利根織物監査役」等歴任されました。
「濱口吉兵衛」は、1868年(慶応4年)7月「紀州広村」(現在の「和歌山県有田郡広川町」)に生まれます。
8代目「濱口吉右衛門」(熊岳(ゆうがく))の「第四子」で「名」は「茂之助」。
「東京帝国大学」卒業。
卒業後、兄の「9代目濱口吉右衛門」が、「政界・経済界」で活躍して多忙であった為、しばらくの間、兄を助けて「家業」に携わりました。
1892年(明治25年)、「濱口儀兵衛」(悟洞)と一緒に「海外視察」したが、その際に「儀兵衛」から「醤油醸造」について様々なことの「教え」を受けることが出来たそうです。
1901年(明治34年)「武総銀行」を設立して「取締役」となり、翌年から3年間は「第一生命保険相互会社」の「監査役」も務めました。
1904年(明治37年)に、兄の「濱口吉右衛門」家から分家し、初代「濱口吉兵衛」を名乗りました。
1906年(明治39年)、「田中玄蕃」の「出蔵(でぐら)」が売りに出た時、「儀兵衛」の勧めで買い取ったそうです。
この時、「儀兵衛」が以前に廃業した「醸造元」から譲り受けていた「ジガミサ」という「商標」を譲渡されました。
1907年(明治40年)、「豊国銀行」設立に参加して「監査役」になる他、「東京護謨工業」や「第一相互貯蓄銀行」の「監査役」などを歴任しました。
1913年(大正2年)、「銚子遊覧鉄道株式会社」(「銚子電気鉄道」の前身)及び「銚子ガス株式会社」の「社長」に就任。
1914年(大正3年)に「家業」を、「田中玄蕃」や「深井吉兵衛」とともに「銚子醤油合資会社」(「ヒゲタ醤油」の前身)として発展させました。
そして、4年後に「株式会社化」した時に「初代社長」となりました。
1920年(大正9年)から「衆議院議員」(二期8年)となった後は、「銚子港」の修築を関係各方面に訴え続けたことで、「国庫補助」による「県営工事」が実現しました。
「濱口吉兵衛」が「初代社長」を務めた「銚子遊覧鉄道(ちょうしゆうらんてつどう)」は、「観光開発」を目論んで建設され、「銚子駅」から「犬吠埼」を結んでいました。
「銚子遊覧鉄道」の「沿革」ですが、1891年6月1日に開通した「総武鉄道」の開通と、「漁業」・「醤油醸造業」・「石材業」の繁栄に支えられた「銚子」界隈では、その貨物運搬と「犬吠埼」への「観光客」に応える「交通基盤」の「整備」が求められていましたことに始まりました。
「総武鉄道」が「延長計画」を1900年5月10日に「外川」までの「延長建設」を認可されましたが、1904年5月12日に「免許」を返納。
1909年には、当時「木更津」・「野田」等に進められていた「県営軽便鉄道」の流れを受けて、「銚子人車鉄道」が再び「県営鉄道」としての実現を試みましたが「千葉県」の「資金的援助」を得るに至らず断念となってしまいました。
再び1912年に施行された「軽便鉄道補助法」に着目した当時「富士瓦斯紡績株式会社」の「社長」であった「浜口吉右衛門」や「ヒゲタ醤油」の創業者「田中玄蕃」等が「株主」となって1913年1月15日、「蒸気鉄道」としての「運営」を目指した「資本金」15万円の「銚子遊覧鉄道株式会社」を設立、同年12月に念願であった「銚子」から「犬吠」間が開通しました。
「銚子遊覧鉄道」は「蒸気鉄道」として開業しましたが、「経営不振」で「第一世界大戦」のおり、「鉄」が高騰したため「レール」や「機関車」を売却してしまい「廃止」となってしまったそうです。
また「濱口吉兵衛」は、「銚子漁港」改修にも力を注ぎました。
その昔、「銚子漁港」周辺は「日本三大海難所」のひとつとして数えられ、当時の「船頭歌」にも「阿波の鳴門か 銚子の川口、伊良湖渡合が恐ろしや」などと諷されていました。
特に「利根川」の「河口」付近にある「千人塚」には、1616年(慶長19年)10月25日に「銚子沖」に吹いた「突風」により亡くなった千人以上の「漁民」を葬ったといわれ、また1919年(明治43年)3月12日にも、「漁船」80隻、「漁民」千人以上が遭難したそうです。
昔の「利根川」「河口」付近は「川幅」が狭く、「川底」には「大きな岩」があり、その上「水深」が浅く、「干潮時」と「満潮時」の「潮の流れ」が急で、一年中「風」が強く吹き「波」が荒い「場所」でありました。
何度も「遭難」が繰り返される中、「銚子の町民」や「漁民」らの間から「河口」を広げ「水深」を深くし、「安心・安全」な「漁港」を造ってほしいという「要望」が上がり、「銚子醤油株式会社」(現「ヒゲタ醤油」)「社長」の「濱口吉兵衛」を「千葉県水産株式会社」「取締役社長」に抜擢し、「安全な港」に修築できるように、「県」や「国」に訴えて貰うことにしたそうです。
以後、「県」や「国」が調査し、「川底」の「爆破」をし「水深」を深くする事を試みるものの、返って「流れ」が急になり、やもなく中止、別の案では、「救助砲」(「救助ロープ」を打ち出す「砲台」)を設置するものの、いざ使用してみると、「船」まで届かず全く意味を成さなかったそうです。
以後、「濱口吉兵衛」は悩み、「漁民」を危険な「状況」から救うため、また「国」へこの実情を訴えるために「国会議員」になる「決意」をしたそうです。
その後、「国会議員」となった「濱口吉兵衛」は、「千葉県議会議員」であった「小野田周斎」と共に「銚子漁港」改修に全力を注ぎ、「銚子港修築案」がついに「国会」を通過、「国」から援助を得ることが決まったそうです。
1925年(大正14年)12月「修築工事」が始められ、1932年(昭和7年)11月に竣工しました。
1937年(昭和12年)「濱口吉兵衛」の「功績」を讃え、「新生河岸公園」に「銅像」が建立されましたが、1943年(昭和18年)、戦時供出されました。
その後、1955年(昭和30年)「濱口吉兵衛」の「銅像」は再建されました。
「濱口吉兵衛」の「銅像」は、今も「銚子漁港」の方を向き、「銚子市」の発展を見守っています。
備考
「濱口吉兵衛」の兄「濱口吉右衛門(9代)」(容所)は、「慶應義塾」を出て、「醤油醸造販売業」、「植林事業」を営んでおりました。
のちに「衆議院議員」となり「財政整理国本培養論」を建策して重視されました。
「濱口吉右衛門」は「鐘淵紡績」重役、「富士瓦斯紡績」・「九州水力電気」・「高砂製糖」社長、「豊国銀行」頭取、「朝鮮銀行」幹事、「濱口」代表社員、「猪苗代水力電気」取締役等を歴任しています。





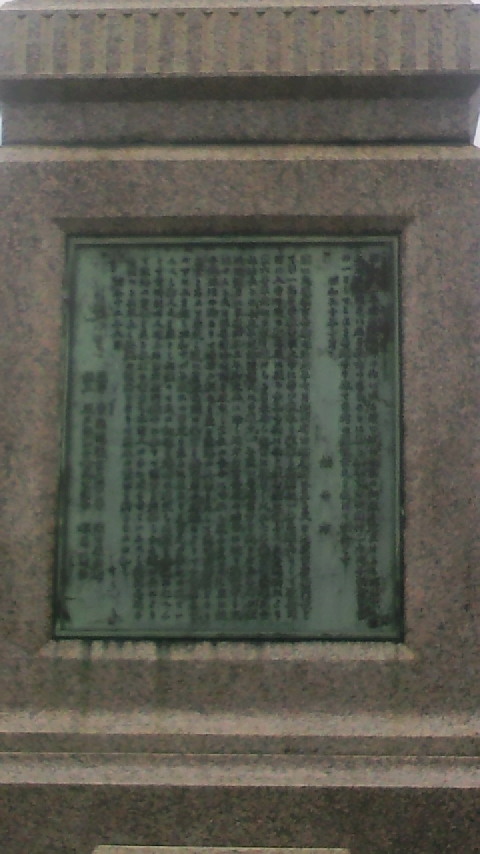


| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=898 |
|
地域情報::銚子 | 09:56 AM |



