本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「多古町」「道の駅多古あじさい館」の近くを流れる「栗山川」沿いにある「あじさい遊歩道」です。
「千葉県香取郡多古町」は、45年ほど前に、「多古町」(前年に「東條村」を併合)・「中村」・「久賀村」・「常磐村」が合併して、現在の「多古町」になっています。
「多古町」は「千葉県」の北東部に位置し、「多古町役場」は「北緯」35.7317「東経」140.4717で、「町」のすぐ脇に「成田国際空港」があります。
「多古町」の「面積」7267平方km・「周囲」54km、年間を通じ温暖で、平均気温は摂氏14度、年間総降水量は1500mmと比較的「多雨」です。
「多古町」は、「北総台地」とその間をめって「水田」が広がる、のどかな「農村」の「町」で、「田」は1800ha(ヘクタール)・「畑」1600ha・「山林」1450haで、約7割の「土地占有率」です。
「多古」という「地名」が付いた「経緯」はいくつかの「説」があります。
「多き古き村」や「田を耕す事」(田子)が転じて「多古」とありますが、一番いわれている「説」が「多湖」説です。
昔「多古町」は、「湖」や「沼地」が多かったので「多湖」と呼ばれていたようですが、「治水工事」や「農地化」により「水」を表す「さんずい」が消えて「多胡」に。
さらに、「夜空」の「月」が「湖」の「水面(みなも)」に映らなくなったので、「月」も取り去られて「多古」になったといわれています。
「生活」と「文化」を育んできてくれた「多古町」の中心を南北に流れる「栗山川」(2月18日のブログ参照)。
「栗山川」への「感謝」の気持ちとして「多古町」では、「栗山川」の「土手」(両堤)約1.2kmに1万株の「あじさい」を植え、昭和55年「あじさい遊歩道」を完成させました。
「あじさい」は毎年「花」をふやし続け、「初夏」ともなると、「紫」、「白」、「薄紅」と色とりどりの「あじさい」が美しい「花の道」を作ります。
「あじさい遊歩道」に咲く「あじさい」ですが、一般的な「日本あじさい」のほか、「ガクあじさい」などが植樹されています。
そして「あじさい」のみならず、「春」には「菜の花」、「秋」には「秋桜(コスモス)」が「川辺」を飾り、訪れる人々の目を楽しませてくれます。
つまり「春」には「菜の花公園」、「初夏」には「アジサイ公園」、「秋」には「コスモス公園」となり、「四季折々」の「公園」になっています。
6月後半には、この「遊歩道」で、にぎやかに「あじさい祭り」が繰り広げられ、付近では、「釣り」や「バードウォッチング」も楽しめます。
また「四季折々」の「花」が咲く「あじさい遊歩道」は、約4kmの「散策コース」にもなっています。
人々の「生活」に「潤い」と多くの「恵み」を与え、子供達を育ててきた「栗山川」に感謝したいといった気持ちにさせてくれる「リフレッシュゾーン」「あじさい遊歩道」。
2001年9月にはこの「あじさい遊歩道」の「景色」を楽しめる「休憩所」「道の駅多古あじさい館」(2010年9月6日・2011年12月24日のブログ参照)も完成し、多くの「観光客」の方、「地元の町民」でいつも賑わっています。
「多古町」の見どころのひとつ「あじさい遊歩道」。
季節の花「紫陽花(あじさい)」の咲く「多古町」へお出かけしてみてはいかがでしょうか?
「あじさい遊歩道」詳細
所在地 香取郡多古町多古1069-1地先 栗山川沿い
問合わせ 多古町役場産業振興課 0479-76-5404
備考
「あじさい遊歩道」近くにある「道の駅多古あじさい館」は、国道296号と「栗山川」の交差する「多古大橋」のたもとに位置しています。
水平に伸びる「田園風景」の中にある「道の駅」で、白い「風車」と大きな「水車」がシンボルで「館内」の「ふれあい市場」では、「多古米」をはじめとする「新鮮・朝採り野菜」や「地元酪農家」の「牛乳」や「アイスクリーム」を販売しています。







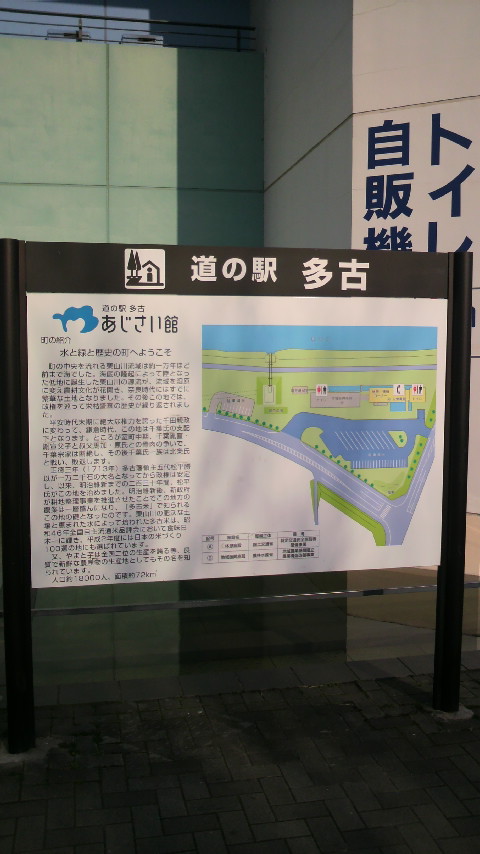


| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=1141 |
|
地域情報::成田 | 07:55 AM |



