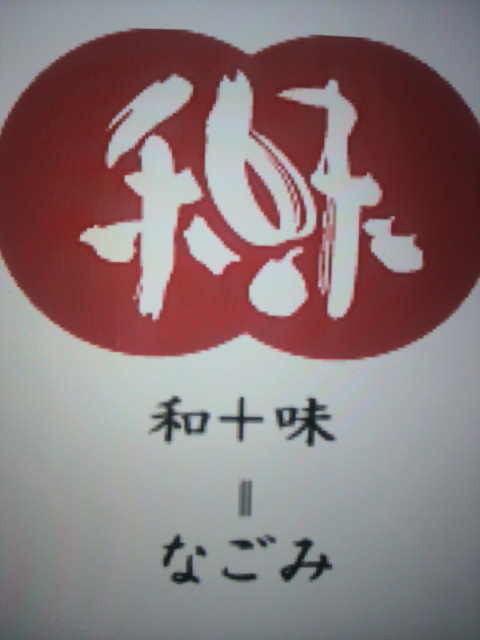本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「成田市」「なごみの米屋總本店」で今週末の10月19日(金)〜21日(日)に開催されます「なごみの米屋總本店10周年特別記念祭」です。
「なごみの米屋」(2011年1月25日のブログ参照)は、明治32年の「創業以来」、「成田山表参道」にて、「季節」の「彩どり」を映した「菓子づくり一筋」に歩んでこられた「和菓子」の「銘店」です。
その「伝統の味」は、地元の「成田」はもちろん、「日本全国」で好評を得ています。
「なごみの米屋」は、「和菓子業界」において「老舗」と呼ばれるまでになりましたが、「伝統」の上で「あぐら」をかくことをせず、「将来」に向けさらに「前進」していこうとするため、「21世紀」の「和菓子文化」の「想像」を目指す上で掲げた「企業理念」が「なごみ」なのだそうです。
この「シンボルマーク」は、「心」の「和」と「おいしい味」、「伝統」と「革新」の「意味」を込めた「2つの円」を重ねた「フォルム」の「和+味」の「文字」を組み込んだものとしています。
優しい「イメージ」の「曲線」に力強い「毛筆文字」が組み合わされた「デザイン」は、新たな「挑戦」を「積極的」に推し進める「決意」を表しているそうです。
この「和」+「味」=「なごみ」こそが、「米屋」の「原点」だそうです。
「なごみ」には、次の4つの「意味」がこめられています。
一.心和(なご)む味の創造
人の心に触れる優しい味わい、五感に感じる味の世界の創造、という意味が込められています。
二.おいしい暮らしの演出
楽しみの食を個性豊かに演出し味のある生活を生む、という意味が込められています。
三.人と人、心と心を結ぶ
人の心を開かせる、心の交流媒体として役割を果たす、という意味が込められています。
四.豊かな未来を広げる
友情や愛情を抱き合い、豊かな未来を創造していきたい、という意味が込められています。
「なごみの米屋」は、この「なごみ」を実践していくことによって、「お客様」の「舌」はもちろん、「心」も豊かにする「お手伝い」をさせていただきたいと考えているそうです。
「ようかんの米屋」から「なごみの米屋」へ。
「味」の「創造」の「延長戦上」に「文化の創造」を見据えて、「なごみの米屋」はさらに「幅広い世代」に親しまれる「お菓子づくり」を目指していくそうです。
「なごみの米屋總本店10周年特別記念祭」は、「なごみの米屋總本店」の「10周年」を記念して行われる「催し」で「日頃」の「感謝」の「気持ち」を込めて、開催されるそうです。
「なごみの米屋總本店」では、「なごみの米屋總本店祭」を毎年開催しており、人気のある「催し」です。
前回行われた「第9回なごみの米屋總本店祭」(2011年10月23日のブログ参照)では、限定の「お菓子販売」や「ガラガラくじ」などを開催。
また「和菓子づくりの実演」や「体験」をはじめ、「餅つき大会」、「成田不動太鼓」など「イベント」が多数行われました。
「なごみの米屋總本店10周年特別記念祭」では、恒例の「3日間限定」「お菓子販売」や「10m羊羹ロールに挑戦」、「ふるまい餅つき大会」、「ちぎり絵体験」、「ふるまい白玉しるこ」、「竹細工体験」、「八街産落花生つかみどり」、「なごみ菓房」、「なごみクイズラリー」、「成田羊羹資料館」「企画展」、「陶器市開催」、「屋台でお祭り」が行われるそうです。
「3日間限定」「お菓子販売」ですが、19日(金)から21日(日)までの「期間限定」で販売され、大人気の「企画」となっています。
「3日間限定」「お菓子販売」では、「里の秋」、「朝焼きどら焼き」(新登場・数量限定)、「深山路(みやまじ)」、「渋皮栗ロール」、「できたて!ハニーカステラ」、「炊きたて赤飯」(各日60箱限定)が販売されます。
また「販売スタッフ」が選んだ「もう一度食べたい商品」という「企画」で、「第1位」「かぼちゃプリン」、「第2位」「醤油餅」が復活、販売されます。
また「總本店祭10周年記念」として、「ぴーちゃんトートバッグ入り」「秋の行楽セット」や「秋のお楽しみ福箱」、「なごみどら焼5個袋入」、「ぱいつつみ林檎3個袋入」が販売されるそうです。
その他、「新栗生栗むし羊羹」、「新栗おこわ」、「ばいつつみ林檎」(新登場)、「ごまみそ大福」、「なごみどら焼くるみ」も販売されています。
また「できたて!ハニーカステラ」は、9時〜、11時〜、13時〜、15時〜と「実演販売」され、「炊きたて赤飯」は11時45分〜販売されるそうです。
「10m羊羹ロールに挑戦」は、「總本店祭イベント」として行われ、「会場」は「お不動様旧跡庭園」前にて10月21日(日)13時から開催されます。
「10m羊羹ロールに挑戦」では、「みんな」で力を合わせ、1本の「ロールケーキ」を「せーの!!」で巻き、出来た「ロール」は、その場で切り分けて食べられるそうです。
「ふるまい餅つき大会」は、10月20日(土)10時〜、15時半〜の2回行われ、「会場」は「お不動様旧跡庭園」前にて開催されます。
「ふるまい餅つき大会」は、1回先着160名の「イベント」で、開始20分前から「整理券」を配るそうです。
「ちぎり絵体験」は、「總本店」2階で開催される「イベント」で10月20日(土)・21日(日)10時〜16時に開催されます。
「京須ちぎり絵教室」により「ちぎり絵体験」が行われ、開催日当日に受付するそうです。
「ふるまい白玉しるこ」は、「お不動様旧跡庭園」前で10月21日(日)10時〜、15時半〜の2回行われる「イベント」です。
「ふるまい白玉しるこ」は、1回先着160名の「イベント」で開始20分前から「整理券」を配るそうです。
「竹細工体験」は10月20日(土)・21日(日)に「總本店」2階で開催されます。
「成田竹工芸保存会」による「イベント」で10時〜16時に行われ、当日に受付するそうです。
「八街産落花生つかみどり」は、10月19日(金)〜21日(日)に「總本店」店内で開催される「イベント」で1回100円で行えます。
「旬」の「落花生」をつかみどり、「千葉県」随一の「生産量」を誇る「八街産」です。
「なごみ菓房」は、10月19日(金)〜21日(日)で「なごみ菓房」で開催される「企画」で「お食事」の方に、「總本店祭」期間中、「プチパフェ」を「サービス」するそうです。
(甘味、ドリンクは除く)
「なごみクイズラリー」は、10月19日(金)〜21日(日)に「總本店」店内で開催される「イベント」です。
当日に受付する「イベント」で、気軽に参加でき、「全問正解」の方に「抽選」で素敵な「プレゼント」をお送りするそうです。
「成田羊羹資料館」では、「企画展」「資料館開設十周年 羊羹展」を8時〜17時半まで開催するそうです。
(通常 10時〜16時)
「陶器市」は、「總本店」1階で10月19日(金)〜21日(日)8時〜17時(21日は16時まで)に開催される「イベント」で、「お茶碗」や「お皿」などの「陶器」を取り揃え行われるそうです。
「屋台でお祭り」は、8時〜18時(21日は16時まで)に「成田羊羹資料館」で開催される「イベント」です。
「屋台でお祭り」では「金魚すくい」2回100円、「輪投げ」1回100円、「綿菓子」1回100円、「ポップコーン」1袋100円、「たこ焼き」6個400円等が行われます。
そのほか、「なごみの米屋總本店」では、10月19日(金)・20日(土)の10時半〜11時と13時半〜14時に「筝」(SOU)の「演奏」、10月20日(土)の11時半〜11時45分に「成田不動太鼓」の「演奏」、10月21日(日)の11時半〜12時に「成田エイサー」、10月21日(日)の14時〜14時半に「キッズフラダンス」が披露されます。
また「感謝企画」として、「各日」先着110名に「紅白饅頭」をプレゼントや、「税込1000円」お買い上げごとに「お買い物券100円」をプレゼント、お買い上げの方全員にお一人様1回、「ガラガラくじ」で「素敵な商品」をプレゼント、また「お子様」に「風船プレゼント」が行われます。
「なごみの米屋總本店10周年特別記念祭」詳細
開催日時 10月19日(金)〜21日(日) 8時〜18時
開催会場 なごみの米屋總本店 成田市上町500
「なごみの米屋總本店10周年特別記念祭」まとめ
10月19日(金)
3日間限定お菓子販売(8時〜18時)
八街産落花生つかみどり
なごみクイズラリー
成田羊羹資料館 企画展 「資料館開設十周年 羊羹展」(8時〜17時半)
なごみ菓房(9時〜17時)
陶器市開催(8時〜17時)
屋台でお祭り(8時〜18時)
筝(SOU)(10時半〜11時、13時半〜14時)
10月20日(土)
3日間限定お菓子販売(8時〜18時)
ふるまい餅つき大会(10時〜、15時半〜)
ちぎり絵体験(10時〜16時)
竹細工体験(10時〜16時)
八街産落花生つかみどり
なごみクイズラリー
成田羊羹資料館 企画展 「資料館開設十周年 羊羹展」(8時〜17時半)
なごみ菓房(9時〜17時)
陶器市開催(8時〜17時)
屋台でお祭り(8時〜18時)
成田不動太鼓(11時半〜11時45分)
10月21日(日)
3日間限定お菓子販売(8時〜18時)
10m羊羹ロールに挑戦(13時〜)
ちぎり絵体験(10時〜16時)
ふるまい白玉しるこ(10時〜、15時半〜)
竹細工体験(10時〜16時)
八街産落花生つかみどり
なごみ菓房(9時〜17時)
なごみクイズラリー
成田羊羹資料館 企画展 「資料館開設十周年 羊羹展」(8時〜17時半)
陶器市開催(8時〜16時)
屋台でお祭り(8時〜16時)
成田エイサー(11時半〜12時)
キッズフラダンス(14時〜14時半)
問合わせ なごみの米屋總本店 0476-22-1661
備考
「なごみの米屋總本店10周年特別記念祭」で「お不動様旧跡庭園」前で行われる「イベント」「10m羊羹ロールに挑戦」、「ふるまい餅つき大会」、「ふるまい白玉しるこ」は、雨天の場合、変更になる場合があるそうです。
また「なごみの米屋總本店」の「3日間限定お菓子販売」は「手作り商品」のため、数量に限りがあるので、万一品切れの際はご容赦下さいとのことです。